大学におけるシステム・ダイナミックスに関する
講義の事例報告
--高知大学人文学部の集中講義について--概要 :
最近、システム・ダイナミックスに関する講義を取り入れようと計画する大学が増
えてきています。筆者(松本憲洋 中央大学研究開発機構・客員研究員)は、東
洋大学国際地域学部・池田誠教授と共に、高知大学人文学部・田村安興教授の
計画にしたがって2001年9月11日から13日まで高知大学人文学部の2、3年生
を対象にシステム・ダイナミックスを中心にした「情報ネットワーク経済論」と題し
た集中講義を担当する機会を得ました。
この体験が、現在講義を計画されている方々にいくらかでも役立てばと思い、内
容について報告します。
1.集中講義の構成
(1)講義の流れ
①
システム・ダイナミックスとそのツールについて、「習うより慣れる」のやり方で
小さなモデルを作りながらモデリング技術について学習
②
社会人の方にコンサルティング・ファームの顧客になってもらって、問題を提起
してもらう。
この形式の狙いは、モデリングとシミュレーションは単にモデルを作ることが目
的ではなく、問題を解決するためにモデリングにより仮想空間での模擬体験を
可能にし、その中から解決策
を導くことであることを体感的に理解させること
です。
ですから、テーマがどんなに立派でも、時間内に途中までしか実行できなけれ
ば、
問題発見->分析->抽象化(モデリング)->
->模擬体験(戦略シミュレーション)->問題解決
の一連の流れを理解できないので学習効果が半減します。
そんなわけで、テーマの選定は特に重要です。
③
学生は興味あるテーマのコンサルティングを引き受けるファームを結成して代
表を決め、顧客との間でコンサルティング契約を締結
④ 顧客とコンサルタントが問題解決に向けて協同作業
⑤
学生のコンサルティング・ファームは、顧客に問題解決結果の報告
⑥
全員が各報告を聞き評価について採点し集計、最高得点ファームの発表
(2)参加者
学生(2、3年生) 21名(最初 25名)
TA(大学院M2) 4名
社会人 5名(民間企業4名、県庁1名)
講師 2名
講師以外の参加者は、システム・ダイナミックスに関して学習の経験がなかった。
また、学生は全員が自分のPCを所有していて、一応のコンピュータ・リテラシは身
に付けていたが、多くは、Excelを十分に使いこなせるレベルにまでは到達してい
ない段階だった。
TAは、システム・ダイナミックスに関する学習の経験はなかったが、コンピュータの
利用技術をはじめ学習レベルが高く、本講座の「習うより慣れる」の時間帯では学
生より理解が早かったので、コンピュータ・リテラシに関する支援だけでなく、シス
テム・ダイナミックスに関しても学生の疑問解決に効果的に活動した。
(3)スケジュール
講義時間は1日5時限を3日間であったが、2日目に6時限目のオプションを付け
た。
(オプションは午後6時から11時まで、70%~80%が参加)
| 期日 |
時限 |
内容 |
| 2001/9/10 |
・・・ |
TAに講義の概要と役割を説明。
学外支援者と問題提起のテーマについて協議し、テー
マを決定。
( 問題提起 -> 分析 ->モデリング-> 解決の一
連のプロセスを演習として実行できるテーマ) |
| 2001/9/11 |
1 |
ガイダンス |
| 2 |
システムダイナミックスとは何か、どんな対象に使える
のか?
・システムダイナミックスの概要を掴む
・
講座で利用するSDツール
・
仮想空間の活用
<SDによるモデリングとシミュレーションに関する
アンケートの提出> |
| 3 |
システムダイナミックスツールを体験的に学習する。
・Studio2001の概要
・ShortShort習うより慣れる
--Studio2001の操作の基礎--
与作さん本舗の製造販売モデルの最低限の機能の
ものを全員が作成し、はじめてのモデルとして各人が
保管。
|
| 4 |
| 5 |
学外支援者による問題提起
・ 四万十川、高知新港、銀行店舗、主力商品、
電力源ベストミックス
グループ分け。 |
| 2001/9/12 |
1 |
モデリングについて人口モデルを使って
昨日の補講
|
| 2 |
モデリングとシミュレーションの演習について説明。
SDを
活用
した問題解決プロセスについて解説 |
| 3 |
各グループへTAを配属。
11
時過までグループ
活動を実施。 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 2001/9/13 |
1 |
各自でシミュレーションを実施し、結果を各人で体験
することにしていたが、高知新港以外はモデルの完
成が遅れ、最後までモデル開発を実施していたグル
ープが多かった。
報告書としては、FDにグループ概要とStudioファイル
を記録して提出。
Studioファイルの内容 :Verbal Model、Causal Loop、
Model、入力条件、結果、問題解決のための分析結果
<報告FDの提出> |
| 2 |
| 3 |
各コンサルティンググループが、クライアントに報告す
る形式で、5グループが工夫 しながら報告。
発表は、主にグループの代表者が報告し、最後に全
員が感想を話した。また、TAも講評した。
発表について全員が相互評価をし、集計結果を発表。
<評価表の提出> |
| 4 |
| 5 |
まとめ
<講義終了後アンケートの提出> |
2.実習に使用したソフトウェア
Powersim Studio 2001 Academic
を講師が持ち込み利用した。
この製品は、日本語でモデルを構築できる。
32人のライセンスがパックになっていて、一人当たりの費用は約4000円である。
この講座を始めた時点で、学生は大学のサーバーに搭載されているプログラムを
各自のPCにダウンロードして実習・演習に使用した。
なお、日本ではPOSY社が販売している。
3.コンサルティングテーマ
① 四万十川の環境容量調査
学生コンサルタント 5人
② 高知電力の電源ベストミックス計画 学生コンサルタント 5人
③ 高知新港のハブ港化と環境評価
学生コンサルタント 3人
④ 銀行店舗のグループ化戦略 学生コンサルタント 3人
⑤ 主力商品の中国戦略
学生コンサルタント 5人
4.成果発表の相互評価
評価の項目は以下の4項目として、それぞれを5点満点で採点した。
① 問題の理解と分析力
② モデルの表現力
③ シミュレーションの適切さ
④ 結果の説得性
評価の基準を決めず相対点で採点したので、点差のばらつきは多きい。評価
する人は各チームに対して最大20点(5点x4項目)以内で、5チームを評価
するので合計100点を配分することになる。
評価の結果によると、そのばらつきは以下の通りだった。
学生 :90 - 61
その他 :93 - 65
そのため、各人の合計評価点を100点にするよう人毎に増幅係数を掛けて解
析した。
評価の結果について、学生以外の順位の傾向は一致した。しかし、学生の評
価順位は、講師達とは大幅に異なったので、この講座の目的、狙い主要点な
どを十分に理解させられなかったのではなかったかと心配したが、以下の結果
から学生全体の評価が我々と異なっているのは単に日常共同生活の影響を受
けているからに過ぎないからではではなかろうかと推論するに至った。
その分析とは、各グループが自分のグループを評価sている順位である。講師
たちが高く評価したグループはそれなりに自分達も高い評価をし、低い評価を
したグループはそれなりに低い評価をしていて、自己評価の相対的順位に限っ
てはどのグループも講師たちの評価に非常に近い結果であった。
さて、限られた時間内にコンサルティングするのであるから、やはり結果の優
劣には大きな差があった。それを学生、講師、TA、社会人がどの程度の格差
で評価したかについて以下にグラフで示す。
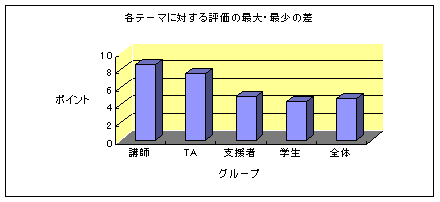
5.コンサルティング演習と発表の状況

最高評価を得た「銀行店舗のグループ化計画」ファーム

本物の外航船船長経験者を顧客にした
「高知新港のハブ港化と環境評価」ファーム

集中力を発揮した「高知電力の電源ベストミックス計画」ファーム

先輩を顧客として団結した「主力商品の中国戦略」ファーム
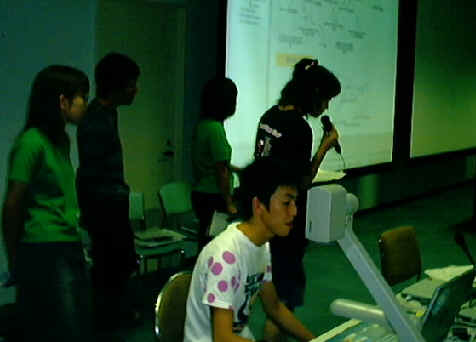
地元の至宝を守る対策に熱中した「四万十川の環境容量調査」ファーム
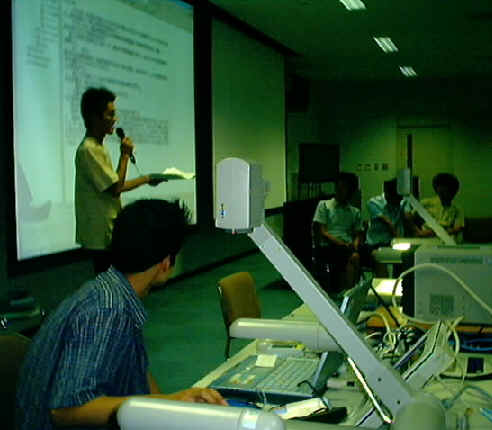
説得力のある説明に成功した「高知電力の電源ベストミックス」ファーム
お問い合わせ
内容についてのお問い合わせはこちらからお願いします。
|